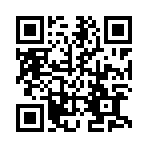2011年05月12日
あの大人気(?)連載が再び…
連載したことがありました。
局地的人気を誇る内容だったのですが、あればかりをここで展開するのも
憚られ、また、私自身ももっと勉強しなければならないこともあり、
しばらくは発信していませんでした。
最近になって、少しずつ、もう一度書いてみようという気持ちになりましたので
「それ専用」のブログを立ち上げました。
まだまだかなりおとなしい内容です。
もうしばらくしたら一般的には「トンデモ本」と呼ばれているようなものからも
得たヒントを基にして、疑問に思っていることをビシビシ書いていこうかと
思っています。
大切なことはいつも隠されている…
日本の歴史は「隠す」歴史のような気がしてなりません。
旧麻植郡で神聖な山とされている高越山も、限られた人の間では
「隠し富士」と呼ばれているのです。
よろしければときどきコチラの歴史ブログへも遊びにおいで下さいませ♪
「藍農家の娘が行く☆四国と忌部の歴史旅」 ← クリックしてください♪
2009年10月30日
カミングアウトしました
やっぱりちょっと、慎重になってしまいました。
「忌部」の二文字を及ばずながら背負うことに緊張してました。
でも、今はスッキリ☆

自分たちが何も知らずに過ごしていた場所が、日本の歴史の重要な場所
であるということを知ることができたのは、藍色工房を立ち上げたからでした。
藍に携わる仕事をしながら聞こえてくる話をたどっていくと、
初めて分かることがたくさんありました。
そして、深い深い感謝の気持ちがわいてきました。
こうして図らずも私たちが受け取った歴史のバトンを、誰かに手渡すことが
できるのなら、愛をもって渡したいなぁ…
そんな日が来ることを願いつつ、正直にもの作りを進めていきます。はい。
2009年05月31日
忌部発祥の神社
2ヶ月以上ほったらかしになっていた、メルマガの連載転載記事シリーズ。
今回は、転載ではなく、最新の書き下ろし記事を挟み込みます。
最新です。
だって、数時間前に、忌部のゆかりの地へ行ったので、感覚が薄れないうちに
書きとどめておきたくって…
訪れたのは徳島県吉野川市山川町の「種穂神社(たなぼじんじゃ)」です。
地元では「たなぼさん」と呼ばれています。
忌部の始祖「天日鷲命(あめのひわしのみこと)」が降り立ったとされる場所に
今も現存する神社で、藍農園の両親はここの神社の氏子です。
この場所に、麻と榖(かじ)と5穀の種と穂を持って、降臨されたと伝えられています。
父と主人は行ったことがあるのですが、実は私はまだ足を踏み入れたことがなかったので
行ってみることにしました。
それで、行ってみた率直な感想を先に言います。
ムリ。
ひとりでは行けません。
また行きたいけど、しばらくムリ。
危ないです。
細かいことは書きませんが、行ってみたい方は以下の点を必ず守ってください。
・コンパクトで馬力のある4輪駆動車でどうぞ。
・タイヤの溝がちゃんとある状態であることを確認してきてください。
・急斜面+シビアな角度のカーブが数か所あり、多少の運転テクニックが必要です。
・梅雨の季節以降、10月下旬くらいまでは行かない方が安全。←なぜかは後ほど
氏子って言ったって、しょっちゅう行くわけにはいかないような場所にあります。
父の軽トラックを借りて主人の運転で途中まで登りましたが、途中で水温計が
あり得ないところまでヒートアップし、車内が少し焦げくさくなったので、あえなく
参道の途中で車を放置。
(だれも来るわけもないような場所で、怒られる心配は限りなく0%)
幼稚園の頃から屋島の登山道で鍛えてきましたが、比べては怒られるような
角度の登山道を、よちよち、よちよち、登りました。
そしてやっと、辿り着いたこの景色。
鳥居がない…
あたりを見渡すと、こんなスペースがありました。
ちょっとした広さのある草っ原です。
小さな白い看板をアップにしてみると。
って・・・。1年にいったい何台の車がここにたどり着けるのでしょうか。
車を降りて歩いていると、斜面が急で大変なのですが、この季節ならではの
楽しみもありました。
シダ類が本当にキレイ!!
アジアの山、っていう感じですよね。
いい!!いいよ!!←早い話がシダフェチ
シダの葉に浮かれている最中に、マムシに出くわしました。
私史上、最接近記録の樹立です。
したがって、5月31日はマムシ記念日。
冗談ではなく、うっそうとした参道の両脇は、これからの季節は相当危険です。
父も時々マムシを捕まえてきてアルコール漬けにして消毒薬を作ったりしているのですが、
ここは、もう夏は歩けないと思う。たくさんいると思う。
そういうわけで、できるだけ参道の真ん中を歩いていきました。
やっとたどり着いたお社は…
鬱蒼とした感じでした。
確かに「種穂神社」って書いてあります。
でも、向かって右側の放置されているシンクは何だ!?
考えたって分からないので、いずれワケが分かっている人に出会ったら聞いてみる
ことにします。
ここから北側に歩いていくと、こんな景色が観られます。
吉野川がよく観えます。来たかったところに来た、という感じがしました。
忌部のご先祖様たちは、ここから吉野川を眺めてどんなことを考えていたのだろう…
そして、お社から南側に行くとこんな立札が。
昔の神社にはたいていセットで存在していた相撲用の土俵跡地があるそうですが…
看板の差す方向はこんな感じ。道が無い…さっきマムシと遭遇したばかりだから
なおさら行けない。
ヘビと言えば、はちきれそうなヘビイチゴもたくさんできていました。
小さな赤丸が足元の所々に現れて、楽しい気分にしてくれました。
阿波において、藍を産業として初めて取り組んだ一族の始まりの場所でもあるので、
私たちにとってもとても大切な心のよりどころであるはずの場所なのですが、
もっと手入れをしたい所ばかりが目につきます。
定期的にここへやってきて、いろいろと手を加えてくださっている方がいるのは
十分承知の上で…地域のみんながもっと気軽にかかわれるような場所にあったなら
もう少し活気のあるお社になっていたと思うのです。
よりによって、ここにあるということの意味は一体何なのでしょう。
なぜ、天日鷲命はここを選んだのでしょう。
「元気いっぱいで仕事をします!!」と手を合わせてお話ししてまいりました。
たどり着くまでも、さらに帰り道も大変でしたが、行ってよかったです。
ずっと気になっていた所に行けて、心の底が、ちょっと落ち着きました。
2009年03月27日
モノ作り集団:忌部氏
久しぶりの更新ですね…
参考書など、ぼちぼちご紹介したい気分ですが、また後ほど。
==============================
阿波と藍と歴史の秘密についてお伝えしている歴史ミステリー
第4弾です。
マニアックな話題についてきて下さり、ありがとうございます。
本日もはりきってまいります☆
前回、忌部氏の名前の由来とその生業について簡単に触れてみました。
神具を作るという重大な役目を担う一族でしたので、「モノ作り」の
ために蓄積されてゆく技術は、おそらく当時の最先端をゆくものであったと
推測されます。
実際に、どんなものを作っていたかといいますと…
・生地を織り、神事に必要な衣服や道具を作っていた
(天皇即位の礼の「あらたえ」、お祓いで使用される「ばっさばっさ」と
神主さんや巫女さんが振り回す「大麻(おおあさ)」などなど。)
・紙を漉き、神事に必要な道具を作っていた
(御幣など)
大きくはこの2点が重要な仕事だったようです。
当時、織り物として用いられた生地は、麻から作られていました。
全て、種を植えるところから始められる作業でした。
それに伴い、畑作業に便利な道具を作る必要性が生じて、いち早く鉄器を
取り入れた道具作りに着手するという流れにもつながりました。
織物を織る技術の発展とともに、糸を紡ぐ技術が必要とされ
繊維を美しく丈夫な糸に紡ぐために研鑽が積まれることになりました。
また、製紙のための楮(かぢ・こうぞ)の栽培も盛んに行われました。
この、神代の時代のモノ作りの技術を起源とする会社が、今も徳島に現存
しています。
●紡糸関連技術で活躍されている「阿波スピンドル株式会社」さん
http://www.awa-spindle.com/jp/jp-index.html
●製紙の技術を今に伝える「アワガミファクトリー」さん
http://www.awagami.or.jp/
こうして、道具作りのスキルを積み、重要な宝物の管理を行い、
祭祀で祝詞をあげ、朝廷に奉仕する集団の拠点として忌部の里が
栄えました。
さて、次回は忌部の仕事の中でも重要な役割を果たした「麻」と、
「藍」の関係について、お話ししてみたいと思っています。
===============================
2009年03月19日
忌部氏の仕事
連載のために文献を調べていると、
「いったいどこまで書いていいものなのか…!?」
と思うような、深くて不思議なことがたくさん出てくるので、ドキドキしました。
とりあえず、どうぞ。
==================================
阿波と藍と歴史の秘密についてお伝えしている歴史ミステリー第3弾です。
今回は、あれ!?となるつながりが一つ、明らかになります。
遠い遠い神代の歴史ロマンに、ご案内いたします。
阿波の国(徳島)に藍を伝えた一族「忌部(いんべ)氏」について、
いったいどんなことをしていた人たちなのか、ちょっとのぞいて
みようと思います。
一般的に「忌部」という言葉には「穢(けが)れを忌み嫌い、神聖な仕事に従事する集団」
という意味があります。具体的には…
・しめ縄(神社で使用されていますね)を作り、穢れを払う
・神意を占う
・宮廷祭祀における神聖な供物を作り、捧げる
といった役割を担っていたとされています。
皇室の「3種の神器」についてお話を聞かれたことのある方も多くいらっしゃると思います。
3種の神器のうちの「鏡」と「剣」は、忌部氏が作る役目でした。
そんな重要な役目を担っていた一族の祖となる人のことを天日鷲命(あめのひわしのみこと)
と呼んでいます。現在の徳島県吉野川市山川町に降臨したと伝えられています。
(天日鷲命が降臨した場所には神社が今でも残っています。
農園に住む私の両親は、その神社の氏子です。)
この、天日鷲命の名前が、あの、天照大神(あまてらすおおみかみ)の
岩戸事件の記述に出てくるのです。
岩戸(正しくは天石屋戸)にこもってしまわれた天照大神に何とか機嫌を直してもらい、
外へ出てきてもらうために、高天原(たかまがはら)の神々は一致団結して
一芝居打つことにいたしました。
平たく言えば、
「天照大神より魅力的な神様が現れたから、とっても愉快で楽しくて
お祭りしちゃおう、バンザ~~~イ!!」
と、みんなでばか騒ぎしたのですね。
そのお祭りに必要な神様への捧げものの一つに「木綿(ゆう)」という
神具があり、それを作ったのが天日鷲命だと記されています。
天照大神…もしかしたら「卑弥呼」かもしれないと言われている人と
忌部氏の祖、天日鷲命は、直接会っていた。
卑弥呼が外交に利用した藍染めの布は…忌部一族の仕事によるもの
という仮説が、現実的になりそうですよ。
おお!!なんか面白くなってきた!!…感じがしませんか?
次回は忌部氏の仕事についてもう少し詳しいお話をお届けいたします。
よろしければ…お付き合いください…
====================================
2009年03月11日
忌部氏
という愛の告白並みの応援をいただいて「局地的人気」を誇る
メルマガの連載コラムの転載記事です。
いろいろ調べているうちに、とんでもない情報が出てきたりするので
深みにはまりながらドキドキしていますが…とりあえず、
連載第2回目をアップいたします。
================================
前回、思っていた以上に反響の大きかった藍と歴史のミステリー。
「おもしろ~~い!!」
とご感想をお寄せ下さった方、ありがとうございます!!
ばんどー、調子に乗っております♪
今回はさらに、歴史のミステリーに迫ってみたいと思います。
はるかな昔、倭の国の女王卑弥呼が魏の国の王に藍染めの布を献上した
というエピソードをご紹介いたしました。
卑弥呼が天照大神(あまてらすおおみかみ)であったとされる説が
有力とみなされるようになる中で、その真偽について知りうる人物が
注目されました。
徳島県吉野川市山川町在住の、三木さんというお爺さんです。
藍色工房の藍農園のご近所にいらっしゃいます。←いきなり身近
この方は、太古の昔からこの地に住まう「忌部氏」の末裔です。
忌部氏は、これまでにもこのメールマガジンやブログでご紹介してきました。
国の神事を司ってきた一族で、今でも天皇陛下が即位する際には
即位の儀式に必要とされている着物をお納めする大役を担っておられる
方々です。
その営みについてはまた別の機会に触れるとして…
(これまた壮大なエピソードになってしまうのです。)
卑弥呼も天照大神も、「神」の声を聞く女王でした。
日本建国の太古の昔から、王と神に仕えてきた「忌部氏」の末裔なら
卑弥呼の墓が本当に徳島に存在しているのか、天照大神が卑弥呼なのか
知っているのではないか、と推測され、注目されるに至ったのです。
歴史ミステリーを追うテレビ番組にまで引っ張り出されました、三木さん。
断り続けて4か月。
根負けして出演を承諾したその末に…
「卑弥呼のお墓は、徳島県にあるのでしょうか!?」
「言えませんな。」
終わり。超クールです。←ハッキリ言って、しびれました
(その時の様子をテレビで見た私は思わず画像をブログに
アップしてしまいました。)
http://aiiro.ashita-sanuki.jp/e17207.html
実は、この忌部氏と藍染めには、深い関わりがあります。
皇室に大切な着物を納めていた部族なので、その着物の染色にも
深く関わって仕事を営んでおりました。
高貴な方々が着用するための着物の生地を染めるために、
徳島で初めて、藍を育て染色をし、それを産業として営んだ
最初の一族でもあるのです。
ここで、モヤモヤしてくる方もいらっしゃることでしょう…
・卑弥呼が魏の国の王に藍染めの布を献上した。
・太古の昔から、高貴な方のために藍染めを営んだ部族が徳島にいる。
・その末裔は卑弥呼の墓のありかを「知らない」ではなく「言えない」と
言っている。
私たちが知っている「日本史」って何なのだろうか…と、ちょっと
ドキドキしてきませんか?
次回は、この忌部氏について、もう少し深いミステリーに迫る
エピソードをお届けしようと思います。
お楽しみに!!
===============================
2009年02月20日
邪馬台国と藍
局地的人気を誇る(笑)藍の歴史コラムの転載記事です。
時々、加筆訂正をしながら、お届けいたします。
==============================
昔むかし。
日本の歴史の中で、おそらく一番古い歴史に残る名前として教わる
女王卑弥呼が、邪馬台国を統治していたというお話は、皆さん
ご存知だと思います。
その出生やお墓のありかをめぐって、さまざまな説があるのですが…
実は、卑弥呼の記録が残されている「魏志倭人伝」に、興味深い
記録が残っています。
倭の国(日本)の女王卑弥呼が、魏の国の王様に藍染めの布を献上した、
という記録です。
藍染めの布がこの時代にすでに存在しており、国同士のやり取りの中で
用いられる贈答品として使用されていた、ということは、やはりとても
貴重なものだったのだと推測できます。
この藍染めの布がどこで作られたものなのか(もちろん邪馬台国
なのですが、その邪馬台国がいったいどこなのか)、ちょっと気になる
歴史ミステリーです。
実は…「卑弥呼」という名前は、日本史の記録には残っていません。
「魏志倭人伝」にしか出てこない人物名です。
近年、この「卑弥呼」に当たる人物が、日本史の中の「天照大神」
(あまてらすおおみかみ)ではないのか、という説が取りざた
されるようになりました。
卑弥呼が息を引き取った際、日蝕が起こり、国中が闇に包まれた
というエピソードと、天照大神が岩戸に閉じこもり、国中が闇に包まれた
というエピソードの共通点に始まり、「同一人物」である可能性が
裏付けられる様々な資料の検証が、続けられているそうです。
そして…その「卑弥呼」=「天照大神」の推測に面白い後押しをする
地域が存在しているのです。
それが、阿波の国「徳島県」。
卑弥呼の墓が存在しているとも言われている山のそばに…
「天岩戸」の案内立て看板がひっそり残されています。
妙です。
「天岩戸」はどこなのか所説はありますが、有力とされてきたのは三重県の伊勢と
宮崎県の高千穂です。
妙です。
だからミステリーです。
このお話…一度でお伝えするには手に余るほど壮大なので、
続きはまた今度。
しばらくの間、藍色歴史物語にお付き合いください☆